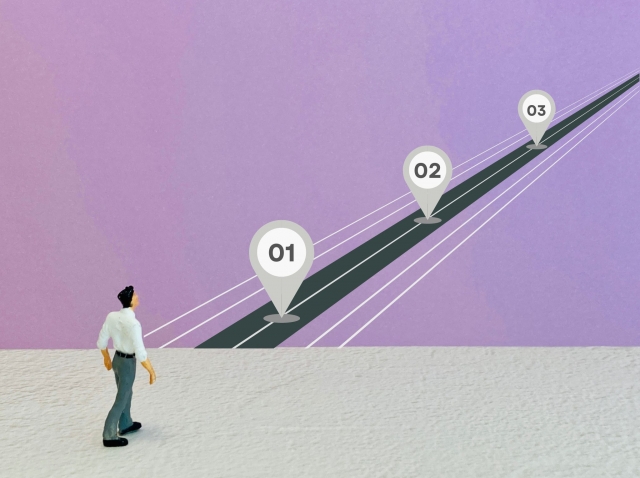親から実家を相続したものの、すでに自分の持ち家がある、実家が遠方にあるなどの理由で、その扱いに頭を悩ませている方は少なくありません。思い出の詰まった大切な場所である一方、空き家のまま放置すれば維持費や管理の手間がかかり、将来的なリスクにもなりかねません。
実家の相続は、多くの人にとって今後のライフプランを左右する重要な決断のタイミングです。
持ち続けるべきか、それとも手放すべきか。そして、手放すのであれば、どのような方法が最適なのか。正しい知識がないまま判断してしまうと、思わぬ損をしてしまう可能性もあります。
そこで本記事では、相続した実家の活用方法から、売却する場合の具体的な手順、かかる費用、そして売却を成功させるためのコツや注意点までを、網羅的に解説します。

宮原海斗(株式会社Gen’Z 代表取締役)
宅地建物取引士/相談診断士

横田大樹(株式会社Gen’Z 専務執行役)
宅地建物取引士/相談診断士
相続した実家を持ちつづける際の活用方法
相続した実家を手放す前に、まずは持ち続けるという選択肢も検討してみましょう。
ご自身のライフプランや実家の状況によっては、有効な資産として活用できる可能性があります。
自身が住む
一つ目の選択肢は、相続した実家に自分自身や家族が住むことです。現在の住まいが賃貸であれば、家賃負担がなくなるため、経済的なメリットは非常に大きいでしょう。また、慣れ親しんだ地域で、親との思い出が詰まった家で暮らせるという精神的な充足感も得られます。
ただし、通勤や通学の利便性、周辺の生活環境が現在のライフスタイルに合っているかを慎重に検討する必要があります。また、建物の老朽化が進んでいる場合は、快適に住むためにリフォーム費用がかかることも想定しておかなければなりません。
賃貸に出す
二つ目の選択肢は、実家を第三者に貸し出し、賃貸物件として家賃収入を得る方法です。安定した入居者が見つかれば、継続的な不労所得となり、老後の私的年金のような役割も期待できます。固定資産税などの維持費を家賃収入で賄える点もメリットです。
しかし、賃貸経営には空室リスクが常につきまといます。また、入居者の募集や家賃の集金、クレーム対応、建物の修繕といった管理業務が発生するため、不動産管理会社に委託するのが一般的ですが、その場合は管理委託手数料がかかります。立地や間取りによっては、賃貸需要がほとんど見込めないケースもあるため、事前に周辺の賃貸市場をリサーチすることが不可欠です。
相続した実家を手放す際の方法
自身で住むことも賃貸に出すことも難しい場合、実家を手放すことを検討します。その主な方法として、「売却」と「相続放棄」があります。
売却する
最も一般的で、多くの方が選択する方法が「売却」です。
実家を売却することで、まとまった現金を手に入れることができます。この現金は、老後の資金や新しい家の購入費用、子供の教育費など、様々な目的に活用できます。
また、売却してしまえば、今後発生する固定資産税や火災保険料といった維持費の負担や、建物の管理・修繕といった手間から完全に解放されるという大きなメリットがあります。特に、複数の相続人で実家を相続した場合、売却して現金化することで、公平に遺産を分割しやすくなり、相続トラブルを回避することにも繋がります。
相続放棄する
売却も困難な場合の最終的な選択肢として「相続放棄」があります。これは、実家を含む全ての相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を受け継ぐ権利を放棄する法的な手続きです。
実家に多額のローンが残っている場合や、資産価値が著しく低く売却が見込めない、いわゆる「負動産」である場合に検討されます。相続放棄をすれば、固定資産税の支払い義務や管理責任から逃れることができます。
ただし、相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があり、一度手続きをすると撤回はできません。預貯金など他のプラスの財産も全て手放すことになるため、慎重な判断が求められます。
実家を売却する際の手順
相続した実家の売却は、通常の不動産売却とは異なり、その前段に相続手続きが必要となります。ここでは、相続手続きから売却完了までの一般的な流れを7つのステップで解説します。
①名義変更を行う
相続した実家を売却するためには、まず法務局で不動産の名義を亡くなった親(被相続人)から相続人へ変更する手続き、「相続登記」を行う必要があります。この相続登記が完了しなければ、その不動産の所有者は法的に確定せず、売却活動を始めることができません。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性もあります。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が実家を相続するのか(または共有名義にするのか)を決定し、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成した上で登記申請を行います。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
②不動産会社に価格査定を依頼する
相続登記の手続きと並行して、売却のパートナーとなる不動産会社を探し始めます。まずは、実家がいくらで売れそうかを知るために、複数の不動産会社に「価格査定」を依頼しましょう。
査定を1社だけに依頼すると、その価格が適正かどうか判断できません。必ず3社以上に依頼し、査定価格とその根拠を比較検討することが重要です。インターネットの「一括査定サイト」を利用すれば、一度の入力で複数の会社にまとめて査定を依頼できるため、手間を省くことができます。
③不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定結果や担当者の提案内容、販売戦略などを比較し、最も信頼できる不動産会社を選んだら、その会社と売却活動を正式に依頼するための「媒介契約」を締結します。
媒介契約には、1社にのみ売却を任せる「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と、複数の会社に同時に依頼できる「一般媒介契約」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、担当者とよく相談し、自分の希望に合った契約形態を選びましょう。
④実家の売却活動を開始する
媒介契約を結ぶと、不動産会社による売却活動が本格的に始まります。不動産情報サイトへの掲載やチラシの配布などを通じて、購入希望者を探します。
売主として重要な役割は、購入希望者からの内見(見学)に備えることです。特に相続した実家の場合、長年住んでいなかったり、遺品が残っていたりすることが多いため、事前の準備が不可欠です。室内の清掃や整理整頓はもちろん、不要な家財道具(遺品)は可能な限り処分しておきましょう。物が少なく、すっきりとした空間の方が、買主は購入後の生活をイメージしやすくなります。
⑤買主と売買契約を結ぶ
購入希望者が見つかり、売買価格や引き渡し時期などの条件交渉がまとまったら、買主と「不動産売買契約」を取り交わします。契約に先立ち、不動産会社の宅地建物取引士から物件に関する「重要事項説明」を受け、契約書の内容を十分に確認した上で、署名・捺印します。この際、買主から手付金(売買価格の5~10%が目安)を受け取ります。
⑥実家を引き渡す
売買契約後、約1~2ヶ月後に、買主から残りの代金を受け取る「決済」と、物件の鍵などを渡す「引き渡し」を行います。決済日には、売主、買主、不動産会社、司法書士が金融機関などに集まります。買主からの入金が確認できたら、司法書士が所有権移転登記の申請を行い、買主に鍵を渡してすべての取引が完了します。
⑦確定申告を行う
相続した実家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署で確定申告をする必要があります。
後述する税金の特例を適用することで、納税額がゼロになる場合でも、その特例の適用を受けるためには確定申告が必須です。売却によって損失が出た場合も、他の所得と相殺できる特例(損益通算)を利用するために確定申告が必要になることがあります。
実家を売却する際にかかる費用
実家を売却する際には、売却代金から様々な費用が差し引かれます。手元に残る金額を正確に把握するためにも、どのような費用がかかるのかを知っておきましょう。
仲介手数料
不動産会社に支払う成功報酬で、売却費用の中で最も大きな割合を占めます。法律で上限額が定められており、「(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税」という速算式で計算されるのが一般的です。
印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙の代金です。契約金額によって税額が定められており、例えば売買価格が1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です(軽減措置適用後)。
譲渡所得税
売却によって利益が出た場合に課される税金(所得税・住民税)です。利益である譲渡所得は「売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)」で計算されます。取得費が不明な場合や、相続した不動産を売却する際に使える税金の特例があるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続した実家を売却する際の注意点
相続した実家の売却には、一般的な不動産売却とは異なる特有の注意点があります。これらを事前に理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな売却に繋がります。
注意点①維持・管理費用がかかる可能性がある
相続してから売却活動が完了するまでの間、実家は空き家の状態になることがほとんどです。しかし、空き家であっても、所有している限り固定資産税や都市計画税は毎年課税されます。また、建物の資産価値を維持するための管理(定期的な換気や清掃、庭の手入れなど)にも手間と費用がかかります。管理を怠って建物が著しく傷んだり、敷地に雑草が生い茂ったりすると、近隣トラブルの原因にもなりかねません。売却を決めたら、できるだけ速やかに行動に移すことが、余計なコストを抑える上で重要です。
注意点②相続登記に時間と手間がかかる
売却の前提となる相続登記は、思いのほか時間がかかる場合があります。特に、相続人が複数いる場合は、誰がどのように財産を分けるかを話し合う「遺産分割協議」が必要ですが、この協議がまとまらないと登記手続きに進めません。
また、登記申請には、亡くなった親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など、多くの書類を収集する必要があります。本籍地が遠方にある場合など、書類集めだけで1ヶ月以上かかることも珍しくありません。売却をスムーズに進めるためにも、相続が発生したら早めに相続手続きに着手することが肝心です。
注意点③特例には適用期限が課されている
相続した実家を売却する際には、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という制度があります。これは、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという非常に有利な特例です。
しかし、この特例を利用するためには、「相続の開始があった日(亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却を完了させなければならない、という期限が設けられています。相続手続きや売却活動に手間取っているうちに、この期限を過ぎてしまうと特例が使えなくなり、多額の税金を納めることになりかねません。この期限を意識し、計画的に売却を進めることが極めて重要です。
相続した実家をどうするか計画的に検討しよう
相続した実家の扱いは、持ち続けるか手放すか、そして手放すならどうやって手放すか、様々な選択肢があります。ご自身の家族構成やライフプラン、実家の状況などを総合的に考慮し、どの方法が最もメリットが大きいかを冷静に判断することが大切です。
もし売却を選択するのであれば、本記事で解説した7つのステップに沿って、計画的に進めていきましょう。特に、売却の前提となる「相続登記」と、税金の負担を大きく左右する「特例の適用期限」は、相続不動産売却における重要なポイントです。
そして、納得のいく価格でスムーズに売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことが不可欠です。複数の会社に査定を依頼し、親身に相談に乗ってくれる、相続案件の実績が豊富な会社を見極めましょう。手続きが複雑で不安な場合は、司法書士や税理士といった専門家の力も借りながら、後悔のない実家売却を実現してください。